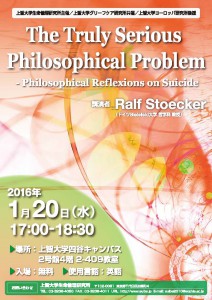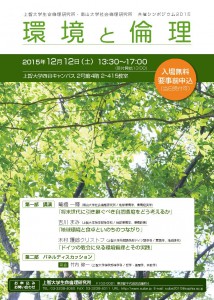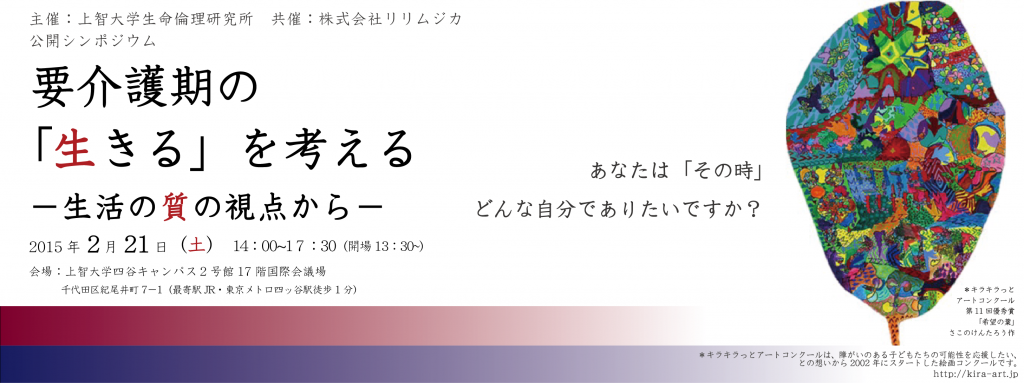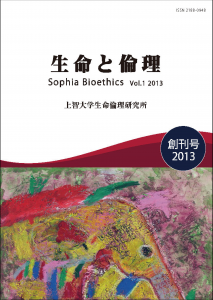上智大学生命倫理研究所・南山大学社会倫理研究所共催
第5回 公開シンポジウム「環境と倫理」
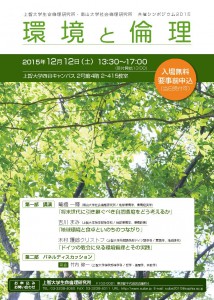
日時 : 2015年12月12日(土) 13:30~17:00(13:00より受付開始)
会場 : 上智大学四谷キャンパス 2号館4階 2-415教室
第一部 講演
▪篭橋 一輝(南山大学社会倫理研究所 第一種研究所員 / 地球環境学、環境経済学)
「将来世代に引き継ぐべき自然環境をどう考えるか」
▪吉川 まみ(上智大学神学部神学科 講師 / 地球環境学、環境教育)
「地球環境と食卓といのちのつながり」
▪木村 護郎クリストフ(上智大学外国語学部ドイツ語学科 教授 / 言語学、地域研究)
「ドイツの教会に見る環境倫理とその実践」
第二部 パネルディスカッション
司会 : 竹内 修一(上智大学神学部神学科 教授 / 哲学・倫理学、宗教学)
参加費 : 無料(事前申込制)
————————————————————————————–
■参加ご希望の方は、以下のフォームよりお申し込みください。

■FAXによるお申し込みは、「環境と倫理」参加申込書
に必要事項をご記入の上、03-3238-4011までお送りください。
■E-mailによるお申し込みは、件名を【シンポジウム参加(お名前)】とし、
本文に、お名前(ふりがな)、ご所属、お電話番号、E-mailアドレスをご記入の上、
suibe2010@sophia.ac.jpまでご連絡ください。
*申し込み締切 : 12月10日(木)
締切後は上記の申し込みはせず、直接会場までお越しください。受付にて承ります。
————————————————————————————–
お問合せ : 上智大学生命倫理研究所
TEL : 03-3238-4050
FAX : 03-3238-4011
E-mail : suibe2010@sophia.ac.jp
開室時間 : 平日9:00~17:00